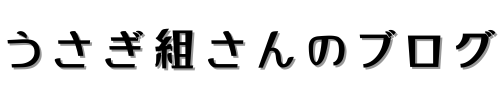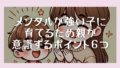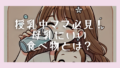魔法の言い換え言葉

子どもの自己肯定感を育むには
親の「声かけ」がとても大切です。
何気なく言った言葉が、子どもの心に深く残り
「自分はできる!」
という自信につながることもあれば、
逆に「どうせ自分なんて…」と
自己否定につながることもあります。
でも大丈夫!ちょっとした
「言い換え」を意識するだけで
子どもはもっと前向きに成長していきます😊✨
今回は、子どもの自己肯定感をぐっと高める
魔法の言い換え言葉 をご紹介します!
今日から使える言葉ばかりなので
ぜひ試してみてくださいね!
言い方ひとつで何倍も伸びる子に…
例:指示を聞いてくれない時

NG→「何回言わせるの?」
この言葉は、子どもに対して「また失敗した」
「理解できていない」と責めるような印象を与えます。
繰り返し言われることで、
子どもは「自分はダメなんだ」と
自己否定の気持ちを抱きやすくなり、
反発したり、やる気を失ったりする原因になります。
OK→「したくない理由があるの?」
この言葉に言い換えることで、
子どもの気持ちに寄り添い、対話を生むことができます。
「なぜできないのか?」と子ども自身が
考えるきっかけになり、親子で解決策を
一緒に見つけることができます。
また、「意見を聞いてもらえた」と
感じることで、子どもの自己肯定感も
高まりやすくなります。
例:なかなか行動に移してくれない時

NG→「さっさとしなさい!」
この言葉は、子どもに「早くしろ」と
命令する形になり、焦りや
プレッシャーを与えてしまいます。
子どもによっては、「何をどうすればいいのか分からない」
「もっと遊びたい」などの気持ちがあるかもしれません。
頭ごなしに急かされると、やる気をなくしたり、
反発したりする原因 になります。
OK→「後どれくらいでできそうかな?」
この言葉に言い換えることで、
子どもは自分で時間を意識し、
「○分くらいでできる!」と考える
きっかけになります。
自分で時間を決めることで、
主体的に行動しやすくなり、
時間管理の意識 も育ちます。
また、親が一方的に命令するのではなく、
「一緒に考える」姿勢になるので、
親子のコミュニケーションもスムーズになります。
例:どうしても手が離せない時

NG→「ちょっと待って!」
この言葉は日常でよく使われますが、
子どもにとっては「どれくらい待てばいいのか分からない」
状態になり、待つことに対するストレスが増します。
特に小さな子どもは時間の感覚が曖昧なので、
「待つ=いつ終わるのか分からない」
と感じてしまい、さらに不安や不満を抱きやすくなります。
OK→「10を3回数えて待っててね」
この言葉に変えることで、
子どもは「具体的にどれくらい待てばいいのか」
が分かり、安心して待つことができます。
また、「10を3回数える」という行動を与えることで、
待つ時間を意識しやすくなり
待つ力(我慢する力)を育てることにもつながります。
例:子供が突然走り出した時

NG→「走らないで!」
この言葉は、禁止するだけで具体的な指示がないため、
特に小さな子どもは「どうすればいいのか」が
分かりにくくなります。また、「走らないで!」と言われると、
子どもは「ダメ!」と否定されたと感じやすく、
反発したり、余計に走ってしまったりすることもあります。
OK→「歩こうね」
この言葉に言い換えることで、
子どもは「今すべきこと(歩く)」が明確になり、
行動を修正しやすくなります。
また、ポジティブな表現を使うことで、
子どもも受け入れやすく、
スムーズに指示に従いやすくなります。
例:子供が失敗した時

NG→「だから言ったでしょ!」
この言葉は、親の「注意を聞かなかったからこうなった」
という気持ちが込められていますが、
子どもにとっては責められているように感じる言葉です。
「怒られるから次は気をつけよう」と思うかもしれませんが、
「どうすればよかったのか?」を
自分で考える機会 にはなりにくく、
ただ萎縮してしまうこともあります。
OK→「どうすればよかったかな?」
この言葉に言い換えることで、
子どもは「自分で考える力」 を
養うことができます。「次はこうしよう」と
学ぶ経験につながり、同じ失敗を繰り返さないようになる
可能性が高まります。また、親が問いかけることで、
子どもは「怒られる存在」ではなく、
「一緒に考えてくれる存在」として
親を信頼しやすくなります。
例:子供が失敗をした時

NG→「ああ!もう!なにしてるの!」
この言葉は、親が驚きやイライラを
そのまま表現したものですが、
子どもにとっては怒られたという印象
が強く残る可能性があります。
特に、子どもがわざとではなく、
失敗してしまった場面でこの言葉をかけると、
「自分はダメなんだ」と自己肯定感が
下がってしまうこともあります。
OK→「大丈夫だよ」
この言葉に言い換えることで、
子どもは安心感を持ち、
落ち着いて行動を修正しやすくなります。
失敗したときに親が冷静に受け止めてくれることで、
子どもは「次はどうすればいいかな?」と
前向きに考えやすくなります。また、
親が安心感を与えることで、
子どもは挑戦や学びの機会を
恐れずに受け入れやすくなります。
例:子供が転んだり怪我をした場合

NG→「痛くない痛くない」
この言葉は、子どもを
安心させようとする意図がありますが、
子どもの気持ちを否定してしまう可能性があります。
実際に痛みを感じているのに、
「痛くない」と言われることで、
「自分の感じていることは間違っているの?」
と不安になったり、親に気持ちを素直に
伝えにくくなったりすることがあります。
OK→「痛かったね」
この言葉に言い換えることで、
子どもの気持ちをしっかり受け止め、
「痛みを分かってもらえた」と安心感
を持たせることができます。
気持ちを共感してもらえた子どもは、
次に「どうすればよくなるか?」を
受け入れやすくなります。
例えば、「痛かったね、冷やしてみようか」と、
解決策につなげることができます。
例:子供が室内などで大声で騒いでいる時

NG→「うるさい!」
この言葉は、親が子どもの
大きな声に対してストレートに
不快感を伝える表現ですが、
子どもにとっては「自分の存在を否定された」
と感じることがあります。特に小さな子どもは、
声のボリュームを調整する力が未発達なため
「どうすればいいのか分からない」状態になり、
悲しくなったり反発したりすることもあります。
OK→「声はこれくらいね」
この言葉に言い換えることで、
子どもは「どのくらいの声ならOKなのか?」
を具体的に理解しやすくなります。
怒るのではなく、「こうすればいいよ」と伝えることで、
子どもも納得しやすく、親の言葉を
素直に受け入れることができます。
また、指示がポジティブな形になることで、
子ども自身も落ち着いて行動しやすくなります。

日々の何気ない声かけも、
ちょっとした言い換えを意識するだけで、
子どもの受け取り方は大きく変わります。
「否定する言葉」から「子どもの気持ちを引き出す言葉」へ。
「命令する言葉」から「行動の選択肢を示す言葉」へ。
こうした小さな工夫が、
子どもの自己肯定感を育み、
親子の信頼関係を深めるカギになります。
完璧でなくても大丈夫!
できることから少しずつ取り入れて、
子どもの心に届く魔法の言葉
を増やしていきましょう😊✨
Tiktokはこちら👇👇